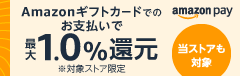ブランド紹介
かもしか道具店

|
|


※ページ下部へ進みます。 |
|
三重県菰野町は、鈴鹿山脈の連なる温泉地。 「鈴鹿セブンマウンテン」という登山スポットでもあり、何よりニホンカモシカ(天然記念物)が生息することで有名です。 そのセブンマウンテンの一番大きな山、御在所岳の麓に“かもしか道具店”を展開する有限会社山口陶器はあります。 「たのしく、しっかりとした生活文化」を発信し、食卓を通じ幸せを届けるブランドです。 |
|

かもしか道具店取材記
|
|
今回は萬古焼の窯元山口陶器さんが作る地域ブランド「かもしか道具店」を取材をさせていただきました。  かもしか道具店のお店(三重県菰野町)
=お店情報=かもしか道具店 〒510-1224 三重県三重郡菰野町川北2834-2 TEL : 059-327-6555 遠目からも目を引く素敵な外観。周辺まで行くと遠くから見てすぐわかります。 実はかもしか道具店を作られた山口陶器さんは当店でも取り扱わせていただいている 4th-marketを構成する4つの窯元のひとつでもあります。ですので店舗に訪れると、かもしか道具店の商品だけでなく4th-marketの商品も購入できます。 予約があればワークショップも随時行われております、湯の山温泉から30分の距離です、ご興味がある方は問い合わせされてみてください。  取材にご協力いただきました皆様。左から山口陶器の山口社長、かもしか道具店の店長さん、作り手から営業まで行う中山さん。 まず最初に、山口さんがどのような想いで地域ブランド「かもしか道具店」を立ち上げたか、今後のビジョンなどについてうかがいました。 産地が存続するには・・・ 山口さんが山口陶器に入ったのは2003年頃です。当時サラリーマンをされていた山口さん、家業である山口陶器を継ぐ事を当時の社長であったお父さんに相談したときに、「やめとけ、やめとけ」と止められたそうです。不景気な萬古焼の焼き物産業継がせることに反対だったそうです。  この言葉が逆に山口さんの気持ちを燃やしました。今が良くないなら自分がこの産地を良くしてやる、「反骨心」そんな気持ちで家業を継ぐことを決意しました。 山口陶器に入社し、萬古焼の産地の現状を目の当たりにしました。当時下請けの仕事を中心としていた山口陶器、需要の波が大きく良い時期はいいけど、注文がない時期はどうしようもない。基本的に受け身で仕事をするのが当たり前。発注元の景気に左右されるし、各種原料の価格変動もあり、安定などとはほど遠い、毎月をどうにかすることで精一杯の状況。 これは山口陶器だけでなく、他の萬古焼の窯元も同じ状況、このままでは今後産地として存続して行く未来が見えない。「これじゃあかんな」と思った山口さん、できる限り外部に左右される要因を減らし、まずは会社としての体質改善から始めることにしました。  そのひとつが2005年の4th-marketの立ち上げです。4th-marketのブランド紹介で詳しくは紹介しておりますが、製造元から小売店への直販をひとつのコンセプトに掲げています。 つまり産地として生き残るために問屋さんとの取引を縮小していったのです。独自の販路構築が必要になりますが、商品の製造から販売まで全体をコントロールでき、自社主導でものづくりが可能になります。産地の、萬古焼のものづくりが存続して行くためにはこれ以外に方法はなかった。 その結果、問屋さんや同業界の人達からは「なんか変わったことしとるわぁ」と冷たい目で見られることも多かったと言います。 歴史のある産地で今までと違うことをする、変えること、これって本当に途方もなく大変なんです。周囲から嫌われる覚悟が無いとできない。聞くと山口さんの場合「気にしてなかった」と言います。「産地を存続させる」という目的に向けて走る山口さんにしてみれば、周囲の目を気にしている暇はなかったとも言えるかもしれません。  全ての話をここでお伝えすることは難しいですが、産地の未来のこと、萬古焼の現状と課題、そこに対して自身は何ができるか など、こんな話をしているうちに私は山口さんの熱さに引き込まれてしまってました。これだけ産地のことを想い、熱く、実行力のある人が“いいもの”を作らないわけがない! かもしか道具店の特徴 4th-market立ち上げから数年、山口さんは次に自社ブランド「かもしか道具店」立ち上げます。三重県の県獣、菰野町の町獣、ともにカモシカなんだそうです。そこからかもしか道具店。  山口さんがこだわったのはかもしか道具店が“地域ブランド”であるという点。あくまでも地域のためのブランド。山口さんのブレない軸を感じます。この軸があるから自信を持って実行できる。 地域ブランドかもしか道具店には興味深い特徴があります。普通、窯元が自社ブランドを作るなら自社で作ります。でもかもしか道具店の場合は少し違う。自社で作れるものも山口さんに共感してくれる協力窯元に依頼してしまう。 協力窯元さんも最初は「えっ?」となったそうです。それはそうですよね、自社でも作れるから。でも、山口さんは言います「産地が元気にならんといかんから」  分野によって山口陶器よりも優れた技術を持った窯元はこの産地にある、自社ではここまで手間かけれないということも簡単にしてしまう窯元もある、そんな作り手の人達がもし産地から消えてしまったらいずれ萬古焼に携わる職人はいなくなる。そんな想いで依頼されているそうです。 実際自社で作る方が早く、コストも抑えれることもあるはずなのに、これができるのは本当に素晴らしいことではないでしょうか。普通の経営者とは視点が違う、まるで産地を経営しているような感覚です。 今回の取材では協力窯元にも訪問させていただきましたが、急に企画会議が始まるんです「こんなことできる?」「こんなん作りたいね」「これ次のかもしか道具店の商品にしよう」とか、立ち話しながら笑いながら。何して遊ぶか決める子供みたいに楽しそうに。  かもしか道具店には『産地のため』という志はもちろんなのですが、根本的に新しい・喜ばれるものを生み出すものづくりが好きな人たちなんだなと。伝え手の私としては少し羨ましくもありました。 産地を元気づける 山口さんに目指すところを聞くと案の上、“山口陶器の”ではなく、“産地としての”答えが返ってきました。 ここ数年は山口さんを中心として、湯の山、四日市など周辺地域と共の活気を取り戻すべく、様々な業界の人たちと、地域の取り組みなども行ってきました。 この取り組みが「まだ“点”なのでもっと広げて“面”にしていきたい」 「そうすることで今は少し離れたところにある観光地の流れで人が来るけれど、この地域自体が人を集める場所にしていきたい」 そんなことを考えられているそうです。  だからかもしか道具店のお店は色々な人が集まれる場所としての機能も磨いていくそうです。地域の人が集まる場所に、観光客が遊びにくる場所に。 かもしか道具点のワークショップエリアでは、本格的な焼き物体験ができます。例えばたくさんある型の中から好きな型を選んで陶土を形成、釉薬も選んでアレンジ。ここは窯元、作家さんが行う陶芸体験ではできない職人体験がここではできます。  それだけでなく最近ではご飯釜で地域でとれた新米を食べるワークショップもされたそうで、すでに人が集まれる場として機能しはじめています。 今はまだお店は“点”ですが、これから発信を続けることで、山口さんの実行力に引っ張られるかたちで、かもしか道具店を端緒に点が線になりいずれは面となって行くのだと思います。 本気でこの地域・産地を良くしたいと思って行動し続けていけば最初に冷たい目で見ていた人も少しづつ力を貸してくれるに違いありません。 製造現場にお邪魔します かもしか道具店のお店近くに山口陶器の工場があります。この場所でかもしか道具店の商品を生産しています。前述の通り一部は協力窯元での生産となっています。 かもしか道具店の商品全てに言えるのですが、デザインがスッキリしていて無駄がなく、機能性もとにかく高い。まさに道具店の仕事、その中でも人気の商品、電子レンジでも使えるご飯釜「ごはんの鍋」の製造行程を拝見させていただきました。 まずは陶土を量り型枠に入れます。  ごはんの鍋専用の設定をした機械に入れておおまかな形を形成。  ごはんの鍋の特徴は内側の出っ張りの部分、これにより吹きこぼれにくく、簡単に蓋がフィットして、使いやすくなっています。蓋をこの出っ張りに載せる形状なので収納性も高いのが魅力なのですが、この形状がポイント。  ありそうでないこの鍋の形状。考えてみると見たことがないですね。これには機械側の特殊な形状と特殊な動きが必要で作ることができるのは、実はかもしか道具店のみだそうです。 そして外側を薄く削ります。  これには2つの意味があります。表面の少しだけ削ることで風合いが全く違って陶器の温かみが増すというデザイン面。そして型から出したままだとツルッとした表面ですが一皮削ることで凹凸ができて表面積が増え火を受けれる面積が広くなり、熱を効率良く受けることができるようになるそうです。 この仕事が実は中々難しいらしく、最近一人職人さんが引退されたため今は山口さんだけしかできないようで、早朝の4時からこの作業をされているとか。 次の持ち手をこれも手作業でつけます。  ここまでできればしばらく乾燥させます。逆さにするのは、乾燥とともに縮む際に歪みがでないようにするため。  次に素焼き。素焼きは約750度~800度で焼きます。素焼きの目的は内側の水分を飛ばすことで釉薬(陶器の塗料)をしっかりと入るようにする。  素焼きが終わればこんな風に少し色味が変わります。そのあとの作業を安定してするために素焼きをするんですね。  その後は各色に合わせた釉薬を付けて、窯で本焼きをします。つまり窯元には最低でも素焼き用と本焼き用の窯がふたつあるということ。こちらが本焼きの窯、大体1,150度~1,250度で焼くそうです。ちなみに窯元ではガス代がめちゃくちゃかかるそうです、だから原油価格の変動は死活問題。  そうしてごはんの鍋は完成します。  見ていただくとわかるように全ての工程に人の手がかかっています。ただ手間をかけているから良いというわけではなく、この行程でしかこれだけの良いものは作れないということ。それでいて道具として幸せを届けるべくできる限り値段も抑えれるように・・・納得感のある価格だと感じるのは私だけではないかと思います。 協力窯元の製造現場へ 自社だけでなく同産地の高い技術を持った協力窯元へ仕事を依頼する山口陶器。今回はかもしか道具店の商品でも1,2を争い売れている「すりバチ」を作られている窯元へ。  普通のすり鉢にあるあの溝がない。けどしっかりすれる。洗いやすくて、すり鉢以外にも小鉢としてもお使いいただける道具。溝を洗うストレスから解放されます。こちらの窯元さんでは生産が追いついていない程だそうです。 では工程を追ってご紹介します。 まずは型に陶土を入れて叩いて広げます。  型ごと回転する機械に置き、親指をうまく使い陶土を均等にひろげます。これが見ていると気持ちいいほどに綺麗に広がります。  こんな具合に綺麗に仕上がります。  そのままでは柔らかくて次の加工ができないので、しばらく乾燥。  しばらく乾燥させて加工しやすくなれば、まずは風合いを良くするために外側を少しだけ削ります。  そして最後にまさかのチョップで片口部分を作り成形の工程は完了。  その後にごはんの鍋同様に素焼き→釉薬→本焼きと進み完成します。 ただこのすりバチは内側の凸凹を作るために釉薬以外に鉄の粉を使います。鉄の粉を撒いてから釉薬をつける。残念ながら今回の取材でその工程は見れませんでしたが、使い勝手・機能性を高めるために様々なアイデアが詰め込まれているのですね。 こちらは素焼き直前のスパイスすりバチ。  ものづくりの可能性 取材を終えて感じたことはものづくりは作り手側が楽しんでいるかが大事なんだということ。もちろん楽しいだけではないはずですが、新しいもの・喜ばれるものを作ることって本来楽しいことのはずなんです。 ただ楽しむには仲間が必要。かもしか道具店には内側にも外側にも仲間がいるんです。それはなによりのモチベーションになるはずです。「あーでもない、こーでもない」と時にはケンカしながらするものづくり。だからこそ良いものが生まれる。 そして一人でも力強い発信を続けることで感化された地域の仲間たちと一層大きな発信ができるようになる。その先には山口さんが目指す産地・地域の活性化があるのだと。  これからも私たちはかもしか道具店から生まれてくる商品たちを本当に楽しみにしています。そしてこれからの萬古焼の産地の変化にも注目していきたいと思います。 今回は大変長い時間をいただき丁寧にご案内、ご説明いただき本当に有難うございました! | ブランド紹介ムービー | |
|

〜 かもしか道具店の商品一覧 〜
ごはんを美味しくする道具たち

ごはんの鍋1合
|
|

ごはんの鍋2合
|
|

ごはんの鍋3合
|
|

ごはんのしゃもじ
|
|

桐のお米びつ
|
|

陶の飯びつ(おひつ)
|
|

おともの器
|
|
|
|
|
|
美味しく便利にする道具たち

しょうがおろし器
|
|

すりバチ
|
|

スパイスすりバチ
|

すりコギ
|
|

だいこんおろし器
|
|
耐熱、直火で使う道具たち

三とく鍋
|
|

ココット
|
|

グリル皿
|

陶のフライパン
|
|

目玉焼き鍋
|
|

陶のやかん
|

陶のすき焼き鍋
|
|

陶のくんせい鍋
|
|

ほっこり土鍋
|

直火のラーメン鍋
|
|
|
|
|
お茶を楽しむ道具たち

ほうろく急須
|
|

しぼり出し急須
|
|
|
「日常を彩る道具達」

蚊遣りブタ
|
|

コーヒードリッパー
|
|

マグカップ
|

ピッチャー
|
|

ポット
|
|

陶のビアカップ
|

陶器の蚊やりスタンド
|
|
|
|
|