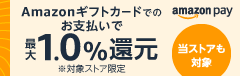ブランド紹介
DAIKURA

|
|

※ページ下部へ進みます。 |
|
DAIKURAは備前焼を産地よりお届けします。 無釉で、絵付けも施さず、窯の中の状態によって焼き物の色や表情が変化する窯変が魅力の備前焼。 先人たちが⻑い時をかけて築き上げてきた「備前焼」を守るとともに、現代の生活に寄り添ったものづくりをこころがけています。 |
|

DAIKURA取材記
|
|
今回は、岡山県の南東部に位置する備前市にお邪魔しました。目的地は、備前焼の産地として知られる「伊部(いんべ)」地区です。 JR伊部駅周辺はレンガ造りの四角い煙突が点在しており、焼き物の町ならでは。通り沿いには、風情たっぷりの窯元やおしゃれなギャラリー、ショップが軒を連ねています。 お話をお伺いしたのは、「DAIKURA」を運営する備前焼作家の小川弘藏さんです。 小川さんは、デザイナーさんと協力してウォーターカラフェの「hiiro」(ひいろ)を手掛けています。 hiiroは、「水がまろやかになる」という備前焼の特性を生かして作られた水差しです。  Photo by Fumio Ando 伝統的な備前焼の技法で焼き上げつつも、デザインはスッとシャープで現代的な佇まい。  Photo by Fumio Ando カラフェの「hiiro」、フタはそのままカップに。飲むときは、カップを外してそのまま中身を注げばOK。おしゃれなだけではなく、実用的に使えるのが嬉しいですよね。  Photo by Fumio Ando 今回の取材では、hiiroとhitoe誕生の話はもちろん、備前焼の特徴から伝統的な作り方まで、いろいろお伺いしてきました。 手作業で作られているのは想像していましたが、実際に見ると予想以上に大変な現場でした。でも、そんな苦労があるからこそ、この美しいhiiroとhitoeが生まれるのでしょう。 今回の取材記では、そのあたりまでしっかりお伝えしたいと思います。 さまざまな焼き色がある備前焼 岡山を代表する、伝統工芸品の備前焼。その歴史は古く、今から約1000年前の平安時代末~鎌倉時代に誕生したと言われています。 しかし同じ備前焼と言っても、赤茶色っぽいものから、青みがかったグレー、黒褐色まで、その色合いは実にさまざま。 「備前焼は、焼き方で色の違いが出るんです。色は違っても、使っている土はすべて一緒なんですよ。土に多く含まれている鉄分が、窯の中の酸素や灰などと化学反応を起こして、こういう風に色が変わります。簡単にいうと、理科で習った『酸化と還元』みたいな感じですね」と小川さん。 「酸素の分量や炭の入れ方、窯を密閉するタイミングなどによって、色の仕上がりがガラッと変わるんです。似たような柄は出せても、まったく同じ柄っていうのは出せない。そういう意味でも、まだまだ奥の深さはありますね」 土の風合い、そのままに 備前焼と言えば、釉薬(ゆうやく)を塗らず、絵付けもしないことで知られています。釉薬とは、陶磁器の表面を覆っているガラス質を生成する薬のことです。 それらを使わずに作られる備前焼は、土が本来持つ素朴な味わいを、よりダイレクトに感じることができます。 「普通の焼き物は、『素焼き』の後に釉薬をかけて『本焼き』という風に2回焼くんですけど、備前焼は釉薬をかけないので1回しか焼きません。他の産地の方には『1発焼きでいいな』と言われることもありますが、1発は1発で結果がシビアに出るんで大変なんですよ…」 なぜ伊部で備前焼の文化が根付いたのか? 備前焼の産地として有名な伊部ですが、なぜこの地で備前焼の文化が根付いたのでしょうか。 「昔から、焼き物に適した条件が揃っていたからでしょうね」と小川さん。 「ここら辺は田んぼの下を掘れば『田土』という、焼き物に適した良質な土が出ました。近くには窯焚きに使う松の木もたくさん生えていたし、山の傾斜を利用して登り窯を作ることもできた。焼き物の文化が発展しやすい環境だったと思います」 備前焼をとりまく、今 こうして伊部で発展してきた備前焼ですが、現在の状況はどうなんでしょうか。 「昔に比べて、窯元も作家さんも少なくなりましたよ。親から子へ継ぐのが一番の近道なんですけど、窯場の子がみんな継ぐというわけでもないです。表の見た目より、裏の仕事がきついんでね(笑)」と小川さん。 「昔は大きな壺や花瓶が主力だったみたいですが、今はほとんど需要がないです。最近は日用品の小さい焼き物が主流ですね。昔と比べて日本人の生活様式が変わってきてるから、作る物も変えていかないと難しくなってきています」 海外での、意外な反応 日本の景気が冷え込んで販売が低迷する中、小川さんたちは海外展開にもチャレンジしました。 「2015年頃、ドイツやフランスの見本市に備前焼を持って行きました。でも現地の人たちには『なに?その汚い色!』と言われましたね(笑)。その当時、向こうは『食器=白』という感覚が強くて、それ以外は理解できないという感じでしょうか」 ところが、しだいに状況が変わってきます。 「その後、海外で日本のお酒がブームになって、日本酒がどんどん売り出されるようになったんです。そしたら日本の文化として、日本人が茶色いおちょこで日本酒を飲んでいるもんだから『それはアリなんだ!』みたいになって。備前焼も受け入れられましたね(笑)。最近はNY売れからも注文が入るようになりました」 日本文化のひとつとして日本酒と一緒に広まっていったのは、伝統工芸品ならではの動きで面白いですね。 備前焼の良さを生かした「hiiro」誕生 「そもそもhiiroもhitoeも、『世界に通用するような物が作りたい』というところから始まったんです」と小川さん。 「当時、伝統工芸品を作っている我々のような人たちと、デザイナーさんをマッチングするというプロジェクトがありまして。そこに参加して、海外展開を前提とした新商品を作ることにしました」  Photo by Fumio Ando 日用品の中でも、ウォーターカラフェというアイテムに行きついたのはどうしてですか? 「デザイナーさんと一緒にどんなアイテムを作るか、話し合いをしたんですけど。最初に備前焼の特徴を説明をして、その時に『水がまろやかになる』っていう話をしたんです。それなら、水系のものを作るのはどうだろうか、と。 備前焼は昔から、「備前水甕(みずがま)、水が腐らぬ」と言い伝えられてきたそうです。水との相性がとても良いので、まさに水差しにはぴったりの焼き物だと言えます。 試行錯誤を重ねた、hiiroの制作 ここからはhiiroの制作過程を追いながら、お話を聞いていきましょう。 「備前の土を使うことと焼き方は今までの伝統的なものですが、hiiroの作り方は試行錯誤の連続でした」と小川さん。 「最初はうちの父がろくろを回して手引きで制作してたんですけど、厚みを揃えるのがすごく難しいんですよ。普通のコップみたいに指が届くものをろくろで作るのはけっこう楽なんですけど、hiiroみたいに細くて背が高いものは指が入らないので、コテを使うんです。これが本当に難しくて…厚みが違うと内容量がだいぶ変わるし、重くて持ちにくくなってしまう」 「僕も縮こまった姿勢でろくろを回してたんで、腰を痛めちゃって。もうこれ無理だ、と(笑)。どうしたらいいか、他の産地の方にも相談しながらかなり試行錯誤しましたね。詳しくはお伝えできませんが、最終的に仕上げで使う治具を工夫することで対応できるようになりました。」 まずは荒削りしていきます。繊細な動きは、まさに職人技! その後はさらにまっすぐ整え、再び手で仕上げの削りを行い、完成です。  画像の左がキレイに仕上げた状態です。 「最初は失敗作ばっかり作ってましたね(笑)。仕上げをする治具はもちろん売ってないので自作しました。改良を重ねて、今は3代目かな」 小川さんは笑顔で話してくれましたが、そこには私たちの想像もつかないような苦労が感じられました。一本一本ここまで手間がかかっているとは、本当に驚きです。 備前焼ができるまで ここからは、備前焼の制作現場を見せていただきました。 「これが、備前焼の原土です。うちでは、田んぼの下から採ったものをブロック状にして、水に浸しやすくしています」と小川さん。色のついた部分が、鉄分の多いところ。ここが化学反応を起こすことで、備前焼独特の色が生まれます。  「ここは土を生成するところです。さっきの土をこの水槽に入れて、板でかき混ぜていきます」 このかき混ぜる作業を少しだけ体験させてもらったんですが、ぐっと水圧がかかり、なかなかの重労働でした…。 「水が濁ったらポンプで吸い上げて、別の水槽に貯めて、今度はそのまま沈殿させます。そして上澄みの水だけをポンプで吸い上げて、また沈殿させてっていうのを繰り返します。そうすると重い土から早く沈殿するので、1番槽、2番槽、3番槽といくほど、だんだんきめの細かい土になるんです」 沈殿させた土は、このドベ鉢という容器に入れて乾燥させます。そうすると、手で練れる状態になるそうです。  DAIKURAの大きな登り窯です。中に棚を組んで焼いていきます。  「焚口に対して、一番正面でしか出ない焼き色っていうのがあるんですよ。僕の曽祖父くらいの時代から、そういう柄や色の違いを追求するようになったらしいです。それまでは大きな窯をみんなで共同で使っていたんですけど、『この場所に置くと、こういう色が出せる』というので場所の取り合いになってしまい、個人個人で窯を持つようになったと聞いています」  こちらは、今メインで使っている薪窯です。 「焼いている途中、焼き物の上にセンバ(炭を運ぶスコップ状の道具)を通して、隙間に炭を入れていきます。再び窯を密閉すると、この炭が焼き物についている酸素を取って燃やす『還元』が起こり、焼き物の色が変わるんです」 炭は、窯に入りやすいサイズにカットして使います。 「炭入れをするとき、壁1枚向こうは1000度以上の高温なんで、けっこう暑いです。暑いっていうより、痛いっていう方が正しいかな(笑)」 薪窯には盛り塩が。炎や炭といった自然が相手だからこそ、成功を神様にお祈りします。  Photo by Fumio Ando hiiroにはレッドとグレーの色の違う2種類の商品があります。これらは価格が違います。 「『色が違うだけでなんで値段が違うの?』ってよく聞かれるんですが、乱暴に言ってしまうと焼き方が違うから値段が変わっちゃうんです。そこまでの工程は一緒なんですけど、1回の窯焚きで取れる量が違うので、どうしても価格に反映されてしまうんです。」 hitoeの模様は「緋襷(ひだすき)」と呼ばれる伝統的な柄です。画像のコップのように、叩いて柔らかくした藁を巻いたまま焼いて模様を出します。 「藁がしっかり密着してると、線がビシッとつく。藁が浮いていると、線がぼやっとした感じになる。窯の中は炎の対流が起きているから、それによって思ったように行かない時もあります」 今回、特別にろくろを回して制作する姿も撮影させていただきました。最近まで体調を崩し、療養中だったという小川さん。「久々にやるんで恥ずかしいですね」と言いながらも、快く制作してくれました。 ごろんとした土の塊が、小川さんの手によってまるで生き物のように動き、あっという間に形になっていきます。さすがですね! これからのDAIKURA 実は私がこの取材に訪れたとき、小川さんは人生の節目を迎えていました。今まで師匠として一緒に仕事をしてきた小川さんの父・秀藏さんが、急な病気で突然亡くなってしまったのです。 「親父は、ろくろを引くのがすごく上手でしたね。徳利なんかは、手元をまったく見なくてもきれいに作れるんですよ。本当にすごかったです」と小川さん。 「亡くなったのがすごく急だったんで、いろいろ引き継ぐ猶予がありませんでした。焼成前の作品もけっこう残っています。親父の残したこれらの作品を次からは一人でちゃんと焚き上げたいですね」と語っていた小川さん。 DAIKURAにとっては、ここからがまた新しい一歩となります。 ものづくりを繋げるということ DAIKURAさんのように、機械ではなく手仕事がほぼ全てに関わるものづくりではだれがどんな想いで作るのかがすごく重要。 取材の所々で思ったことは「もっと楽に作る方法があるのでは?」ということでした。 おそらくそんな方法は小川さんたちはすでに知っていて、やろうと思えばできることもあるはずです。でも、取材を終えて「あっそういうことではないんだ。」とわかりました。  工数を減らしたり、「これで良いか」と少し基準を下げたり、機械を入れて量産できるようにしたり。その繰り返しが味わいのないものづくりを産んでしまう。 必ずしも、旧来のやりかたを堅持することが正解ではないかもしれませんが、簡単な方簡単な方に流れていくものづくりにおそらく私も魅力を感じないと思います。 取材をしていて、小川さんたちの頭には、クオリティの高いものを安定して生み出す工夫はあっても、手間を省くとか、楽をするというような発想がないと感じました。 おそらくお父様から引き継いだのは技術だけでなく、こうした想いの部分は大きかったんだろうなとお話をしていて強く感じました。ものづくりを繋げるってこういうことか、と。 そんな意味では小川さんには、メモを取らないお父様からものづくりの細かなノウハウは引き継げていなかったとしても、備前焼の窯元の作り手として最も重要な部分はしっかり引き継げているんだと思います。 これから初めてお父様がいない窯入れをされる小川さん、待ち受けている壁はたくさんあるかもしれませんが、小川さんなりのものづくりをしっかりと確立されていくのだと思います。 それと同時に、私たちは微力ながら小川さんのような作り手さんの生み出す価値をしっかり伝えれるように頑張らないといけないなとも改めて感じました! 長時間の取材にお付き合いいただき、ありがとうございました。 可愛い看板猫のすずちゃんも、ありがとうございました。 | 製造現場ムービー | |
|
DAIKURAの商品一覧

カラフェ hiiro
|

カップ hitoe
|