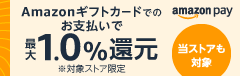ブランド紹介
深海産業(Broom Craft)

|
|

|
|
Broom Craft 歴史ある箒の作り方をもとに、スタッフによって新たに生み出された独自の製法を加え、職人がひとつひとつ手作りで製作しております。 棕櫚・シダ箒の持つ深い歴史を、人の手で大切に繋いでいきたい。 未来に、そして世界へ。 そんな想いを胸に、日々丁寧に心を込めて、物づくりと向き合っています。 |
|

深海産業(Broom Craft)取材記
|
|
青く晴れ渡る空に、緑豊かな山々、広がる田んぼ。 今回の取材記では、日本の原風景のような景色が広がる和歌山県海南市にやってきました。  和歌山を代表する特産品といえば、みなさん何を思い浮かべますか? パッと思いつくところでいえば、梅のトップブランド「南高梅」や、甘くてジューシーな「みかん」でしょうか。 ですが、和歌山にはまだまだ隠れた特産品があります。それが、今回お邪魔した「深海(ふかみ)産業」さんの手がける棕櫚(しゅろ)製品です。 棕櫚という言葉、初めて聞いたという方もいらっしゃると思います。 棕櫚とは、いわゆる「ヤシの木」に似た木の一種。私たちが暮らしの中で目にするものでいえば、箒(ほうき)の穂先やタワシなどに使われる素材です。 深海産業では、そんな棕櫚の歴史を未来に繋いでいこうと、オリジナルブランド「Broom Craft(ブルームクラフト)」を立ち上げ、さまざまな商品を制作しています。  こちらは看板商品の国産棕櫚箒。サイドにほどこされた三つ編みがトレードマークです。耐久性が高く、丁寧にお手入れすれば20年30年と長く使用することができます。   その他、フライパンにこびりついた油汚れを落とすのに便利なキッチンブラシや、気になるところが手軽に掃除できる手帚など、ラインナップも豊富。 今回の取材記では、聞き慣れない棕櫚という素材についてはもちろん、深海産業が作る箒の制作秘話から製造現場の様子まで、たっぷりお届けします。 この取材記を通して、みなさんが棕櫚という素材を知り、箒をもっと身近に感じていただければ嬉しいです。 棕櫚って、なに? 「Broom Craft」が手がける棕櫚の箒は、しなやかで柔らかい掃き心地が特長。 また、繊維に適度に油分が含まれているので、埃を舞い上げずに掃くことができ、畳やフローリングに艶が出てくるワックス効果もあるとか! 知れば知るほど箒の素材として優秀な棕櫚ですが、そもそもどういった植物なのか、詳しく教えていただきましょう。お話をお伺いしたのは、スタッフの津村 昴さんです。  はじめに、加工する前の棕櫚を見せていただきました。棕櫚は、木の幹を覆っている皮の部分を製品に使用します。  まるで人が織ったかのように、格子状になっていますね。これがまったく人の手が加わっていない“自然の状態”というから驚きです! 「もともとこのあたりの山には、棕櫚の木がたくさん自生しています。一説には、高野山の弘法大師・空海さんが『これは産業になる』と言って広めたとも伝えられているんですよ」と津村さん。 時代とともに移り変わる、棕櫚の今 ここまで話を聞くと、地元に生えている棕櫚を使って箒を製造しているのかと思いますが、現在、素材の棕櫚自体は中国から輸入しているそうです。 なぜ国内に生えているのに、わざわざ輸入するんでしょうか?  「昔はこのあたりに生えている棕櫚を原料にして箒やタワシを作る地場産業が盛んだったのですが、時代とともにだんだんと下火になっていきました。今ではそのほとんどが、スポンジや歯ブラシといった家庭用品を取り扱う会社に変わっています。今の日本では、棕櫚の木が生えていても、その皮を剥ぐ人がほとんどいない状況です」  そもそも棕櫚の木というのは、皮を剥がされると、より強くなろうとしてどんどん硬い皮を生み出す性質があるそうです。人間の皮膚も、外部から刺激を受けると皮が厚くなったり、硬くなったりしますが、まさにそれと同じ。 逆にいうと、皮を剥がないと皮はやわらかいまま。せっかく棕櫚の木があっても、皮を剥いで手入れする人がいない今の日本では、やわらかい皮しかとれません。 「そのやわらかさを生かして、今でも一部のタワシ作りには使われているようですが、ふにゃふにゃし過ぎて箒作りには向いてないんです。なので、うちは棕櫚の素材に関しては中国に頼っています。中国の方が圧倒的に質が良いんですよ」と津村さん。 未来を見据えて始めた、箒作り もともと深海産業は、1950年頃に先代の深海 洋治さんが自宅で棕櫚縄の生産を開始したのがはじまり。それ以来、70年以上にわたって棕櫚縄を製造し続けてきました。 棕櫚縄は、主に緑化資材として活用されています。 例えば、街路樹が倒れないように添え木をあてて結ぶのに使ったり、竹垣の竹を組むのに使ったり。最終的には自然に還るエコな素材として重宝されており、深海産業が日本国内で95%のシェアをもつそう。  「ですが、なかなか時代の流れもあって、棕櫚縄だけではいけない、と。なにかしようというところで始めたのが箒作りなんです」 それが2019年のこと。会社としては歴史ある深海産業ですが、箒作りに関していえば、まだまだ歩き始めたばかりなのです。 きっかけは、京都からの依頼 では、箒を作ろうと思った最初のきっかけはなんだったのでしょうか。当時の事情を、専務取締役の深海 耕司さんに聞きました。 「僕が各地の職人さんを訪ねて回っていたときに、京都の荒物を取り扱う商店の女将さんから依頼を受けたんですよ。京都のシダ帚を作る職人さんがいなくなってしまい、このままでは伝統が途絶えてしまう。なんとかしてシダ帚を復活させてくれないかって」  シダとは、パルミラという木の葉柄部分(葉を支える枝の部分)から取り出す繊維のこと。京都ではこのシダを使った箒が昔から使われ、「京帚」や「庭帚」などと呼ばれていました。 棕櫚とシダは似た素材なので、棕櫚縄を扱う深海産業ならなんとかできるのではないかと女将さんは考えたのでしょう。 「いただいた箒を解体して、職人みんなで研究し、なんとか納品はできたんですが。やはり箒に関しては素人なんで、クレームが発生してしまいました」 クレームから生まれた、独自の製法 クレームの内容は、「帚の毛が抜ける」というもの。いきなり大きな難題にぶつかった深海産業ですが、ここから本領を発揮していきます。 「僕らはいい意味で全員が素人のところからスタートしたんで、変な固定概念がないんですよ。今まではこうして作っていた、こうしなければいけないっていうのが、何もなかったので。純粋に『どうすればよくなるか』だけを突き詰めて考えました」と深海さん。 「なぜそういうことが起こるのか」「どうしたらいいのか」。職人が一丸となって問題と向き合い、解決策を徹底的に考えました。そうして生み出されたのが、毛を抜けにくくする独自の製法です。  もともと箒は、毛をまとめた束(これを玉と呼びます)を合体させてできています。 画像の「従来」と書いてある玉が、伝統的な製法で作ったものです。芯に対して毛を巻きつけるだけですので、使い続けるうちに毛が抜けてしまうことがありました。 画像の「新規」と書いてある玉が、深海産業独自の製法で作ったものです。今までとは倍の長さの毛を用意し、芯に巻きつけてから折り返して銅線で留め、その上にさらに毛を足す。そうすることで、従来よりも毛が抜けにくい仕様となりました。 もちろん、今までより時間も手間もかかりますが、使い心地を一番に追求するからこそ考えつくことができた製法です。 トレードマークとなる、三つ編みの誕生 京都の伝統製法に独自の製法を加え、シダ帚を見事に復活させた深海産業。そのノウハウを生かして棕櫚箒の制作にも取り掛かりますが、こちらでも、また難題にぶつかりました。 それが、箒を使うときに最も力が掛かるサイド部分の「強度」です。一般的な棕櫚の箒はこの部分に銅線を巻くことが多いのですが、使い続けるうちに銅線が切れたり、ゆるんだりしてしまいます。 銅線を巻かずに、強度を保つ方法はないか。それを突き詰めた結果生まれたのが、商品名にもなっている三つ編み(TRECCIA)。棕櫚をぎゅっと編み込むことで強度をキープしつつ、見た目にもオシャレな佇まいに仕上がりました。  「うちは女性の職人が4人おりまして、女性からの意見も取り入れています。…でも正直言って、最初僕は大反対したんですよ」と笑う深海さん。 「そもそも僕は三つ編み自体やったことがないので、それを棕櫚でするっていう発想がなくて。三つ編みだと、可愛すぎるんじゃないかと思ったんです。今は、うちしかやっていない製法ですし、特に女性の方に可愛いとご好評いただけて良かったな~と(笑)」 伝統を守りつつ、進化していく 「うち独自の製法で箒を作っているので、本当に“伝統工芸”かっていわれると、どうなんだろうと思う部分もありますけど…」 伝統をそのまま受け継いでいくことももちろん大切ですが、深海産業は問題を問題のままにせず、時代に即して、より快適な使い心地に進化させていくスタンスをとっています。  「見た目は伝統に則った形で、使い勝手としては従来の物よりいいものを、ということで常にアップデートできるようにしています」と深海さん。 進化を続ける一方、伝統を守りたいという想いから、深海産業では“職人育成プロジェクト”に取り組んでいます。これは、年齢・性別・経験の有無を問わず、箒作りのノウハウを伝えていく仕組み。 「職人さんが技術を止めてしまって、弟子にしか教えないというのでは、伝統が止まってしまう。誰でも作れるような工程でカリキュラムを組み、『ここ、こうしたらやりやすかったよ』とか、社内で情報共有しながら箒作りができるようにしています」と津村さん。  箒作りに限らず伝統的な物作り全般に言えることですが、おじいちゃんが一人でやっていて、誰も後を継がないということがよくあります。現に京都のシダ帚も、そうやって一度途絶えてしまいました。こういったことがまた起こるのを防ぐ、画期的な取り組みですね。 生き生きとした、楽しい制作現場 ここからは、箒の制作現場にお邪魔します。 箒という商品から、いわゆる職人気質的な空気感をイメージしていましたが、いい意味で裏切られました。性別も年齢も社歴も関係なく、和気あいあいとした楽しい雰囲気があふれています。  「みなさん家庭もあるし、子どももいるんで。例えば今日は風邪を引いたからって急に休んだり早退してもOKです。やっぱりそういう働き方をしたほうがいいですよね」  「商品を作るっていうのは反復作業なんで、しんどい部分もある。ゆとりを持ちながらやるっていうのが大事です」と深海さん。その言葉通り、工房内は楽しい会話が飛び交います。そうやってワイワイ話をしつつも、作業する手は少しも止まらないのがすごいところです。  「僕らは職人のイメージっていうものを払拭したいんですよ。箒だけじゃなくて、どの業界もそうだと思うんですけど、職人が少なくて若い人がやりたくないっていう背景には、『難しそう』とか、『職場の環境が悪そう』とか、そういうイメージがあるんだと思います」と深海さん。  「うちは見ての通り、堅物に取り組んでるっていうわけでもなく、楽しくやっています。もちろん、『楽しく』の中でも、きっちりやるところはやりますよ。お客様にちゃんとした商品を届けたいんでね」  こちらは、棕櫚箒の三つ編みをしているところです。髪の毛をおさげに編んでいるような感じですね。「髪の毛を編むときとは、ちょっと力の掛け方が違います。上に向けて力を掛けていく感じ」と職人さん。  三つ編みの数や長さなどは、特に決まってないそうです。 「玉を合体させて組んでいくときに、一度編んだものをほどいて調整したりするので、作ってみないと分かりません。なので、箒の一本一本が、本当に世界にひとつだけなんですよ」  こちらでは、箒の玉を作っています。ある程度大きさを揃えて個体差が出ないようにするため、同じ職人さんが手掛けるそうです。  こちらが、玉の芯となる部分。深海産業で取り扱っている緑化資材の余りを巻いて作っています。これ自体も天然素材なので、深海産業の箒はどれも環境にやさしいものばかりです。  職人さんが使ってる道具も、各自で使いやすいようにカスタマイズされています。 こちらは銅線を締めるのに使う道具ですが、本来は電気工事用に使うものなんだそう。手前が新品の状態で、奥がカスタマイズした状態です。奥は、黒い持ち手の部分を削って握りやすくしているのが分かりますね。  これも、元々はプラスドライバーでしたが、先を落として削り、自作したものだそうです。専用の道具を揃えるわけではなく、例えば100均で見つけてきて改造するなどして、自分たちで使いやすいものを作っています。これも、既成概念にとらわれない深海産業ならではですね。  「こういった作業用の道具とかにしても、製品にしてもそうなんですけど。もっといい方法があるんであれば、ちょっとずつでも、いいものにしていきたいです」と深海さん。常に前進し続ける姿勢に、感銘を受けました。  ちなみに、今回の工房見学中に、キッチンブラシの制作体験をさせていただきました。先ほどご紹介した道具を使って銅線を締めて、中に折り込む作業に挑戦します。ひと通り説明をしてもらったのですが、やはり見るとやるとでは大違い!  足を踏ん張って体重をかけながら銅線を締めるのですが、想像以上に力が必要です。途中で銅線が切れてしまうハプニングもありつつ(笑)、なんとか完成させることができました。ありがとうございました。 棕櫚製品を、未来に繋いで 最後に、今後の展望をお伺いしました。 「あんまり世界中でバンバン売りたいっていうよりかは、地元に昔からあったものを、まず地元に知ってもらって。それが徐々に日本全国で『いいものやね』って広まっていけば、いちばんいいかなと思っています」と深海さん。 「江戸時代から棕櫚の産業はあったんですけど、今、地元の子どもたちに棕櫚ってなにか聞いてもひとりも知らないんですよね。その現状をなんとかしたいです」と津村さんも語ってくれました。 最終的には、和歌山県といえば、梅、みかんだけじゃなくて、棕櫚製品もあるということを知ってもらいたいそうです。  「僕らはビルみたいな建物を建てることも、大きな橋を架けることもできないですけど。未来に棕櫚製品を残せたら、自分の人生ハッピーやったなと思います。それをみんなでやっていきたいです。伝えていく自信はあるんで」 そう力強く語る深海さんをはじめ、スタッフの全員の背中には、「CRAFT WITH PRIDE(クラフト ウィズ プライド)」の文字が。 誇りをもって取り組む深海産業のみなさんなら、きっとその未来を実現できるはずです。  深海産業さんのものづくりでは国内の素材に固執することなく、作り方についても柔軟で、取り組み姿勢や環境も他とは少し違った印象をうけます。 考えられていることは「より質の良いものをより作りやすく」、そして何より「箒作りが次代にも続けられる産業になること」。 伝統に縛られて変われないものづくりはいずれ消えてしまう。これは多くの作り手さんの取材にうかがって感じていることです。「唯一、生き残るのは変化できる者である」ということですね。 積み重ねてきたものを変えるのは勇気がいりますが、その点深海産業さんはフラットな気持ちで取り組めたのが良いものを生み出せたのだと思います。 伝統を守るのではなく、大切にし、その芯の部分を理解すれば、それ以外の部分を変えることは日本ものづくりにとって今求められていることだと感じました。  深海さん、津村さん、深海産業のみなさま、長時間にわたる取材にご協力いただき、ありがとうございました! |
|

Broom Craftの商品一覧

国産棕櫚箒 | トレシア
|

国産シダ箒
|

国産棕櫚の万能ブラシ | トレシア
|

国産棕櫚の万能ブラシ
|

国産棕櫚・シダの手箒
|

国産棕櫚の鍋敷き
|