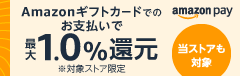ブランド紹介
槙田商店

|
|

|
|
1866年江戸末期に創業。織物の製造から傘の組み立てまで一貫して生産することができる、世界で唯一の老舗織物工場。私達の作る傘は、すべて織生地です。服地づくりで培われた技術と傘を組み合わせることで他にはない傘を生み出しています。日本最高峰の職人が、伝統技術をもって、「あなただけの特別な傘」を実現します。 人生を添い遂げたくなる傘をお楽しみください。 |
|

槙田商店 取材記
|
|
山梨県南都留郡にある槙田商店さんでは、江戸時代から続く織物の技術を活かして傘を作っています。今回はそんな槙田商店さんのこれまでの歩みやものづくりに込められた想い、こだわりについてお話を伺いました。  
郡内織物の歴史と甲斐絹の広がり 山梨県の郡内地域は、織物の産地として有名です。この地域で作られる甲斐絹(かいき)という絹織物は「先染め織物」といってまず糸を染め上げてから織られます。  槙田商店の始まりは江戸時代、1866年に創業しました。当時は江戸に年貢として米を納めるのが一般的でしたが、山や坂が多い山梨から重い米俵を運ぶのは難しく、また行商人もこの地域から商品を仕入れるのは困難でした。 そこで運びやすく価値の高い絹織物が年貢として納められるようになり、山梨の甲斐絹が全国に知られることになったのです。 その後幕府から贅沢禁止令が発令され、一般人が表立って派手な暮らしができなくなりました。 そこで江戸で大流行したのが、羽織の内側に模様を施す「裏勝り」。この裏勝りの流行を機に甲斐絹はますます広がっていったのです。 布産業の発展と槙田商店の傘づくりの始まり 槙田商店では古くからある地場産業の絹織物を発展させ、独自の技術を活かした傘づくりに取り組んでいますが、その始まりはどのようなものだったのでしょうか。槙田商店の栗原さんにお話を伺いました。  「槙田商店はもともとは生地屋なんです。創業当初は生地の仕入れや販売に始まって、その後衣服用の布地を制作していたんですが、昭和になってポリエステルが発展したことで絹産業全体が縮小してきました。」  「そのタイミングで郡内の各織物の会社が、ネクタイやストールなど自分たちの得意分野に商材を絞って発展していったんです。当時の槙田商店では傘、服、マフラーなんかの生地をつくっていました。」 そう話す栗原さん。傘づくりはいつどのようなきっかけで始められたのでしょうか。 「傘用の生地を織り始めたのは50〜60年ほど前で、当時は百貨店で傘を販売する大手のメーカーさんに生地を納めていました。傘づくりを本格的に始めたのは20年ほど前のことで、ちょうど百貨店での傘の販売が減ってきた頃ですね。」  「大手のメーカーさんからの依頼が減ってきたタイミングで自分たちでデザインした生地を織って組み立て、販売までやってみようということになったそうです。というのも、あくまでメインではなく細々となんですが、実は一部傘の状態にしてから製品として納めていたものもあったんです。おかげで傘を作るノウハウがあったというわけなんです。」 傘の生地を作ってきたノウハウを生かしての傘づくりと販売。苦労されたのはどんなところでしょうか。 「今でも大手の傘メーカーさんに生地を卸しているので、私たちが作った傘をデパートに置かせてもらうわけにはいかないんです。お客様が競合になっちゃうので。なので今はセレクトショップに置かせてもらったり、ポップアップショップやてしごと展で販売しています。」 糸を染め上げるところから始まる傘づくり 生地から傘を作っているとのことで、まずは織機のある工場を見せていただきました。  オリジナルの傘を作り始めたのは会社の歴史としては最近だという事ですが、槙田商店の織物や傘にはどのような特徴があるのでしょうか。 「織物で傘を作っている会社は他にもありますが、糸を染め上げて生地を織って、傘を組み立てるところまでを一社で行っているのは日本でもここだけだと思います。」  「うちの工場は織機のサイズが大きいので、ジャガードの織りの模様が大きく作れるんです。ちなみにこの織機はなかなか繊細なので、室温や湿度も年間を通して一定に保つ必要があって、ちょっと暑いくらいがちょうど良いんです。」 細かな温度管理まで必要になってくるんですね。 ところで、この美しい模様はどのようにして作られているのでしょうか。 「縦糸を持ち上げて、その下を横糸が通れば縦糸の色がでて、反対に横糸を縦糸の上から通せば横糸の色がでます。それらを細かく繰り返すことで絶妙な色の濃淡や細かい柄が表現できるんです。デザインの色に制限はありますが、その制限の中で美しい柄を作ろうと頑張ってます。」  工場で目の前で折られていく布は光の加減によって表情が変わり、この段階でもすでに見惚れてしまうほどなのですが、このあと防水加工を経てより美しく光るそうです。 細かい分業制で成り立つものづくりと課題 最初の行程の「撚糸」では、染め上げる前に糸をカセというドーナツ状にする「カセ上げ」という作業が行われます。 その次はその状態で染める「カセ染め」をする染色屋さん。さらにそれを巻き取って縦糸を12000本以上並べる成形屋さん。  というように、槙田商店での傘づくりにはたくさんの人が関わっています。想像以上の細かい行程ですが、分業をしている事で苦慮されている点についても教えていただきました。 「分業での傘づくりに関わっている、どこかの会社が廃業になってしまうと続けることができないという点です。」 「どの会社もかなり細かく分担された作業を行っていて、どこが欠けても成り立たない。そんな状況の中でそれぞれが後継問題を抱えているんです。実際にこのあたりでは後継がいないために仕方なく工場を畳むところが多いんです。」  「地域の内職屋さんにお願いしている作業はコストを抑えることにも繋がっているのですが、その方達が高齢化で辞めてしまったり、新しく募集するには賃上げの必要もあって…これもうちだけではなく産地全体の問題ですね。」 郡内地域でのものづくりと同じことを他の地域でやろうとしても、各工程の段取りを行う体制がないからできない。改めてここでしか作れない貴重なものだということが分かりますね。 大型の機械だからこそできる繋がった柄 織物の模様は裏側から見ると色が反転していますが、昔はこの模様を作るのに「紋紙」というものが使用されていました。  紋紙というのは穴が空いている巻物のようなものです。これを織機にセットすると織機が紋紙の穴の情報を読み取って模様を表現するそうです。 「今はうちでは紋紙の代わりにUSBのデジタルデータを機械に読み込ませていますが、まだ紋紙を使っている工場もあります。受注の量によっては外の機屋さんにお願いすることもあるんですが、そこでは今も紋紙を使って模様を作っているんですよ。」 同じ織物でも工場によって違いがあるとのことですが、槙田商店で使う機械にはどんな特徴があるのでしょうか。 「この機械を使うと長いリピートの柄が作れるんです。傘の生地を作るのにここまで大きな織機を使っているのは、うちくらいなんじゃないかなと思います。」  「傘の三角形の面をコマというのですが、隣り合うコマを跨いだ大きな柄を作ったりもできます。さらにこの機械では、70cm× 2 の140cm幅に交互にコマを配置して織っていて、これだと効率も良いし、無駄になる生地が少なくて済むのも特徴です。」 元々傘用に作られた機械というだけあって、こだわりや工夫がたくさん詰まっているんですね。 全体のチェックと生地の裁断 生地が織り上がったら、検反機という機械を使って140cm幅の状態で生地の表側から50m分を一気に確認し、全体に模様のエラーや汚損がないかを探します。  その後生地の裁断作業に入ります。織機で織られる生地幅が140cmそれを半分の幅に折り、専用の木型を使ってコマと呼ばれる三角形の形に切っていきます。傘の生地はこの段階ではすでに防水加工が施されているため、専用の建ち包丁が使われています。  「大抵8コマで一本の傘になるんですが、傘によって形も色々なので、それぞれの骨に合わせて、使う木型も変わってきます。」  「たとえば女性用の傘は60cm程度が一般的なんですが、同じサイズでも傘のデザインに依って切り方が変わるので、たくさんの木型があるんです。ちなみにうちでは少し深さのあるお椀型の形の傘が人気ですね。」 実際に使うところを想像しながら 裁断した後は再度生地のチェックをします。  検反機では、どうしても細かい傷などの見落としが起こる可能性があるため、裁断後は実際に使う時をイメージしてより細かく見ていく必要があるそうですが、どんなところに気をつけているのでしょうか。 「まずは表側から光を当ててエラーがないかを確認します、しかし大事なのは裏側なんです。傘の表面って買った時には見るかもしれませんが、実際に使う方が良く見るのは裏側なんです。なので裏側にエラーが出てないようにしっかりと確認をしていく必要があるんです。」  「傘を刺して太陽の光で透けた時に初めて細かい傷に気づいた、なんてことにならないように生地の表側から光を当てた状態で透かして見ていきます。」 実際に使う方の気持ちに寄り添い、使う方が気づかないほどのエラーも見逃さない厳しいチェックによって、槙田商店の高い品質の傘が生まれているんですね。 エラーからヒットした商品 織り上がった段階でエラーになった生地はB反、C反として販売されることもあります。 しかしコマ用に裁断した後にエラーが見つかった場合は、生地として販売する事ができません。そのため傘を止めるバンドなどに利用されてきましたが、もっと利用できるところはないかと考えられて生まれた商品がエコバッグです。  「主に裏側にエラーがでた生地を再利用してエコバッグを作っています。傘を刺すときは内側にエラーがあれば問題ですが、エコバッグになってしまえば使っていて全く気になりません。」 「防水の加工が施されている生地なので、冷たいものを入れた時の水滴なども染みてこないところも人気の理由なんです。また同様にカバーバッグも作っています。突然雨が降ってきた時に大切な鞄が濡れないようにするバッグです。」 なるほど、傘の防水加工とエコバッグやカバーバッグとしての再利用はとても相性がいいのですね。  エコバッグを作る上で大変なことなどあれば教えてください。 「ちょっと問題というか、ありがたいことにエコバッグやカバーバッグが本当に良く売れるので、エラーの出た生地だけでは生産が追いつかなくなってしまって。今では普通に作っているんですが、今までは不要になった布で作成していたものを一から作成するとなるとコストが上がってしまうんですよね。」 特殊なミシンで行われる「中縫い」 さて、裁断とエラーの確認の後は「中縫い」という作業に移ります。ここではコマにした生地をつなぎ合わせていくのですが、この工程にはどんなこだわりがあるのでしょうか。  「中縫いに使うミシンは一般的なものとちょっと違って、下糸がないんです。この特殊なミシンを使って上糸だけで縫うことで、傘を広げた時に弾性が効いて生地が綺麗に張るんですよね。」  もし通常のミシンで縫うと、傘が開きにくかったり、しわが入ってしまうそうです。より綺麗に仕上がるように、使う道具や機械にも工夫がたくさんあるんですね。 「槙田商店の傘づくりは、地域の中での分業になっています。工程ごとに専門の会社があったり、内職屋さんが担当していたり、みんなで作っている傘なんです。うちで働いてくれてる内職屋さんは個人の方が多いのですが、高齢者や外で働けない人に生地と骨を持っていって作っていただき、後日回収しています。」 地域で一体となって作り上げる槙田商店の傘づくりには、地域に働く場を生み出すという意味もあるんですね。 骨に縫い付けていく「縫いとじ」 コマを縫い合わせたものをカバーと呼ぶのですが、次はこのカバーを骨に取り付けていく「縫いとじ」と言われる工程です。  専用の金具を使って生地と生地の間に骨を取り付けていくことにより、弛んでいた生地がピンと張り、美しさがより際立ってきます。 「縫いとじも基本的に地域の内職さんにお願いしてるので、それを回収してここで検品をするんです。傘の表面に糸が出てはいけないので、そこは特にしっかりと確認しています。」  「その後ドライアイロンをかけて、上に 陣笠というものをつけて雨が入らないようにします。最後に手元の部分をつけて終わりなのですが、手元をつけて保管すると嵩張るのでつけない状態で保管し、商品として出す直前につけているんです。」  内職屋さんから回収したあとの検品も含め、それぞれの工程の中で何度も厳しくチェックされてやっと出来上がる槙田商店の傘。 仕入れる糸によってエラーが出ることもあれば、織機で織る際にエラーが出ることもあり、防水の加工で塗りが荒い事でエラーになってしまうことも。 各段階でのエラーを何度も細かくチェックしていくところに、作り手の方々の職人としてのプライドを感じます。 一から作れることの強み 実は槙田商店では傘を「作っている」だけではないそうです。 「有料にはなるんですが、うちで買っていただいた傘に関しては全てお直しが可能なんです。」  「それが結構依頼があるんですよ。最近も自転車に巻き込まれちゃったと言って持ってきた方がいらっしゃっいましたしね。傘の骨が折れてしまったり、生地に穴が空いてしまった場合も修理をしています。」 大きく破損してしまった場合にも直してもらえるというのは嬉しいですね。これはまさに生地からつくっているからこそできる対応だなと感じました。 では修理の対応ができないケースはあるのでしょうか。 「生地から作っているので、穴が空いてしまったコマだけ取り替えることはできるのですが、廃盤になってしまって別の生地を提案をすることもあります。」 作るだけではなく修理まで責任を持って行うことで、愛用する傘を長く使っていただきたいという槙田商店の皆さんの思いが感じられます。  しかしコマを張り替えるとなると、解いてまた縫い直すということですよね。結構大変な作業なのではと思うのですが、どうなんでしょうか。 「確かに作業は大掛かりになる時もありますが、サービスの気持ちで手間賃だけいただいて対応しています。せっかく気に入って買っていただいたんですから、そのあともできる限り寄り添っていきたいなと思っています。」 コロナ禍で見えたEC需要と課題 現在、傘の販売はECサイトがメインとなっているそうですが、その背景にはコロナの影響があったそうです。 コロナ禍ではデパートが休館し、大手の傘メーカーさんからの発注が減りました。そこで何とか売り上げを作ろうと、ECサイトでの販売を拡大させていったそうです。 コロナで影響を受けたことは他にもあったのでしょうか。 「コロナの時には全体的に需要が減りましたね。特に売れ行きが落ち込んだのは折り畳み傘です。折り畳み傘って旅行に持って行ったりするじゃないですか。でも今となっては、あの時期にECサイトを拡大出来たのは良かったと思っています。」 そう話す栗原さん。  ECサイトで販売する上で、何か大変な事などはありますか。 「うちの商品の売りはジャガード織の生地なんですが、ECサイトではどうしても生地の風合いが表現しきれないという所でしょうか。動画なども載せて伝えようとはしているのですが、やはり直接見て欲しいなという気持ちはありますね。」  確かに実際に機械で織り上げられる生地を目にした時、ECサイトで見た以上の感動がありました。 さらに店舗に並ぶ商品を見て、生地が傘の形になることで、曲線に沿ってジャガード織の表情が輝きを増すことに気がつきました。これはECサイトで見ていてもなかなかわからないことだなと感じました。 日本いいもの屋としても動画での紹介など検討していきたいと思います。 地域とともに歩む槙田商店のこれから 最後に、この地域でものづくりを続けていくことに対する思いについて伺いました。 「この地域は、他の傘屋さんや織物工場さんととにかく仲が良いんですよ。 」 「私はここでのものづくりしか知らなかったのでそれが当たり前だと感じていたのですが、実は最近、他県で織物を作っている人たちと交流する機会があって、他では同じ織物の仕事をしている人同士がライバル関係だと聞いてびっくりしました。」 同じ業界だと必然的にライバル関係になってしまうのかと思っていましたが、なぜ郡内地域ではそんなにも横のつながりが強いのでしょうか。 「郡内地域の布産業は、座布団地、カーテン地というように商材が決まっているので、良い関係でやっていけているのかもしれません。」  「それぞれが発展していく過程で、ただ得意分野に分かれただけなんですけどね。同じ傘を作る会社同士でも織り方が違ったりするので、うちに来た依頼でも他の傘屋さんの方が合っている時はそちらを紹介することもあります。」 他の傘屋さんを紹介するなんて、驚きです。強みに合わせて発展していったからこそ、それぞれに個性があり、お互いがぶつかることなくものづくりを行っているんですね。 今後に対する想いについてもお聞きしました。 「この辺りだと一軒家に見えても織機があったりして、親世代だと、機械の音が聞こえて今よりももっと身近に感じていたみたいです。私の世代になるとだいぶ廃れてきたのでもう知らない人も多いんですが、廃れゆく産業だからこそ仲間同士助け合って盛り上げていこうと頑張っているんです。」  「つい先日隣の富士吉田市主体で行われたハタオリマチフェスティバルにも参加してきたんですが、これからも地域を盛り上げようという仲間意識を大切に、みんなでものづくりをやっていきたいと思っています。」 地域全体の強い絆を大切にしながらものづくりに取り組んでいく、槙田社長・栗田さん・槙田商店の皆さま、長時間位わたり取材にご協力いただき、ありがとうございました。  左が槙田社長、右が栗原さん |
|

槙田商店の商品一覧